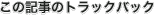空はあんなに青いのに…
youtube mychan
https://www.youtube.com/user/mitaraijisho/videos?view=0&view_as=subscriber&shelf_id=0&sort=dd
COMICS
Profile
Recent Comments
CATEGORIES
つぶやいたー
My List
F_Link
Music
Return to Forever - The Romantic Warrior 1976
Return to Forever - Beyond the 7th Galaxy 1975
Jimi Hendrix - Purple Haze
Miles Davis - Human Nature
Sonny Rollins -Airegin
WesMomtgomery FullHouse
The Beatles - Strawberry Fields Forever
Debussy - 1st Arabesque
Horowitz plays Chopin Ballade 1
Wagner - Die Walküre
チャイ6「悲愴」第一楽章 - カラヤン
三つのパラフレーズ
Zigeunerweisen
Dualis - ひばり
Shostakovich, Symphony No. 5,Bernstein
Michael Jackson - Beat It
To Zanarkand
友川かずき 生きてるって言ってみろ
友川かずき トドを殺すな
Recent Entries
(03/03)
(02/09)
(01/06)
(08/08)
(04/01)
iTunes
ブログ内検索
Counter
Access Analysis
サイバークローン
著作権表示
トリックスター:© 2011 GCREST
ソウルキャリバーⅣ:©1995-2008 NBGI C9:(c) WEBZEN, Inc. All Rights Reserved. Licensed to (c) GameOn Co., Ltd.
ソウルキャリバーⅣ:©1995-2008 NBGI C9:(c) WEBZEN, Inc. All Rights Reserved. Licensed to (c) GameOn Co., Ltd.
22
龍臥亭なんだけどこの小説めちゃくちゃ面白いと思う。
石岡くんが事件を解く、つまり凡人がこの超難易度の犯罪を解き明かすわけである。その為、推理のプロセスが明確に順序よく把握できるように構成されている。壮大なプロットであり、濃い密度があるこの本を読んでいる感想としては他の小説とは別格の印象を雄弁に受ける。ネタバレ記事を書いているので今回で終わろうと思う。事件の顛末・解説はこんなところに書くべきではないといまさらながら思うので。
龍臥亭 第七章
石岡くんとミチがミチの夜10時の墓地参りに行き銃撃された次の夜、ミチは今夜も行くと言う。
石岡くんは里美にユキを頼み、二子山一茂と坂出小次郎にも協力を仰ぎ、ミチを尾行する。
無事ミチが拝み終わった後、一茂が墓地の向こうの茂みで白いものがあると言うので、ミチを待機させ、3人はこれに近づく。坂出の案により、3人は三方に別れて腹ばいでこれに進む。石岡くんはそれが人影であることに気づいた。しかもそれは2人いるようだ。近づくのが億劫になるが興味も同時に滞在する、すると坂出の声がした。坂出はもう到着したようだ。そして二人は倉田エリ子と犬坊一男の死体を発見する。清らかな死体であった。清らかという表現である理由の一つに何故か死体のそばには二冊の本があったからなのである。基督教の賛美歌集と北原白秋詩集であり、今までのような残酷な死体現場ではなかった。
次に発見された死体は守屋と菊子であった。これらは最初石岡くんが貝繁村に来た時に通ったバス停の近くである。守屋は停留所の待合室で、菊子はバス停から少し行ったところの道の脇に置かれていた。守屋は失踪時とは服装が違い、服が一度脱がされた形跡があった。菊子の死体に新聞紙の包みが置かれていた。この新聞紙は不細工な鳥の絵が描かれていた。その中身は守屋の性器であった。これは何を意味するんだろう。
石岡くんは事件を必死に考え、御手洗のような超人的な閃きも無ければ記憶力もないので、物書きなんだから文章を書いていた方が頭は回転するから事件を整理しながら推理する。被害者の表をつくり共通項を探した。この事件の謎は多数あり、それはつまりその数だけ真相へのアプローチが可能であるのだ。
まあ省略。
現在下巻の180頁。石岡くんが里美の学校の図書館で阿部定事件について事件の内容を知った後、犯人が過去の事件の見立て、要するに過去の事件を参考にした部分があるのではないかと考え、昭和年表本を見ながら犯人が知りえた情報を探している。津山三十人殺しについて昭和十三年の桜の頃と言っていたから四月の頁を見るが見当たらなかった。おしいなあ、これ五月なんだよ石岡くん、どんまい。
石岡くんは阿部定事件のあった昭和十一年をざっと見たが他に猟奇的な事件は無かった。津山三十人殺しも見つからない。本を閉じ、これは違ったかとしばらく考えた。ここで読者が考えるべき事は何が違ったか?を石岡くんと同時に考えるべきであるというのがぼくの考えだ。
ぼくはこれを怠り行を進めてしまった。
御大の筆は進み、間違ったと言ってもこれは二通り考えられる。今回の龍臥亭事件のテキストを実事件に捜すという発想そのものが違っているという考え方、これが一つ。もう一方は、追求の考え方は間違っていないが、昭和十一年という場所が違っているという考え方。
本を閉じ、これは違ったかとしばらく考えた。ぼくもしばらく考えるべきであり、これは二通りの考えられる、というプロセスを歩まねばならなかった。このままでは石岡くんに先をこされるし、いつまでたっても読者が今までの御手洗と石岡くんの関係みたくいつも答えを待つという姿勢は即刻辞めるべきだ。そういう意思をこの本を通じて感じる。
180頁4行目、しかし、ではそうであると仮定して、いったいどこを捜すのか。が現在である。これを今考え中だ。これを考えついた後に次の行を読もうと思う。昭和2万日の記録を全て捜すのは無理なので絞らないといけないがどこを捜すか。これは津山三十人殺しの記録を捜すべきなんじゃないだろうか。もしくは阿部定事件を知りながら解釈の違いを犯した犯人を考えると日本人であるという可能性をやめ、外国人の犯罪記録を捜すのもいいかも知れない。
なんてなことを考えながらまあ読み進めていく次第です。個人的には一男が死んだのだからもういつでも中庭のリュウ壊した方がいんじゃないかなんて事は思う。TSのメンテ終わったしこの辺でお開きにしよう。
石岡くんが事件を解く、つまり凡人がこの超難易度の犯罪を解き明かすわけである。その為、推理のプロセスが明確に順序よく把握できるように構成されている。壮大なプロットであり、濃い密度があるこの本を読んでいる感想としては他の小説とは別格の印象を雄弁に受ける。ネタバレ記事を書いているので今回で終わろうと思う。事件の顛末・解説はこんなところに書くべきではないといまさらながら思うので。
龍臥亭 第七章
石岡くんとミチがミチの夜10時の墓地参りに行き銃撃された次の夜、ミチは今夜も行くと言う。
石岡くんは里美にユキを頼み、二子山一茂と坂出小次郎にも協力を仰ぎ、ミチを尾行する。
無事ミチが拝み終わった後、一茂が墓地の向こうの茂みで白いものがあると言うので、ミチを待機させ、3人はこれに近づく。坂出の案により、3人は三方に別れて腹ばいでこれに進む。石岡くんはそれが人影であることに気づいた。しかもそれは2人いるようだ。近づくのが億劫になるが興味も同時に滞在する、すると坂出の声がした。坂出はもう到着したようだ。そして二人は倉田エリ子と犬坊一男の死体を発見する。清らかな死体であった。清らかという表現である理由の一つに何故か死体のそばには二冊の本があったからなのである。基督教の賛美歌集と北原白秋詩集であり、今までのような残酷な死体現場ではなかった。
次に発見された死体は守屋と菊子であった。これらは最初石岡くんが貝繁村に来た時に通ったバス停の近くである。守屋は停留所の待合室で、菊子はバス停から少し行ったところの道の脇に置かれていた。守屋は失踪時とは服装が違い、服が一度脱がされた形跡があった。菊子の死体に新聞紙の包みが置かれていた。この新聞紙は不細工な鳥の絵が描かれていた。その中身は守屋の性器であった。これは何を意味するんだろう。
石岡くんは事件を必死に考え、御手洗のような超人的な閃きも無ければ記憶力もないので、物書きなんだから文章を書いていた方が頭は回転するから事件を整理しながら推理する。被害者の表をつくり共通項を探した。この事件の謎は多数あり、それはつまりその数だけ真相へのアプローチが可能であるのだ。
まあ省略。
現在下巻の180頁。石岡くんが里美の学校の図書館で阿部定事件について事件の内容を知った後、犯人が過去の事件の見立て、要するに過去の事件を参考にした部分があるのではないかと考え、昭和年表本を見ながら犯人が知りえた情報を探している。津山三十人殺しについて昭和十三年の桜の頃と言っていたから四月の頁を見るが見当たらなかった。おしいなあ、これ五月なんだよ石岡くん、どんまい。
石岡くんは阿部定事件のあった昭和十一年をざっと見たが他に猟奇的な事件は無かった。津山三十人殺しも見つからない。本を閉じ、これは違ったかとしばらく考えた。ここで読者が考えるべき事は何が違ったか?を石岡くんと同時に考えるべきであるというのがぼくの考えだ。
ぼくはこれを怠り行を進めてしまった。
御大の筆は進み、間違ったと言ってもこれは二通り考えられる。今回の龍臥亭事件のテキストを実事件に捜すという発想そのものが違っているという考え方、これが一つ。もう一方は、追求の考え方は間違っていないが、昭和十一年という場所が違っているという考え方。
本を閉じ、これは違ったかとしばらく考えた。ぼくもしばらく考えるべきであり、これは二通りの考えられる、というプロセスを歩まねばならなかった。このままでは石岡くんに先をこされるし、いつまでたっても読者が今までの御手洗と石岡くんの関係みたくいつも答えを待つという姿勢は即刻辞めるべきだ。そういう意思をこの本を通じて感じる。
180頁4行目、しかし、ではそうであると仮定して、いったいどこを捜すのか。が現在である。これを今考え中だ。これを考えついた後に次の行を読もうと思う。昭和2万日の記録を全て捜すのは無理なので絞らないといけないがどこを捜すか。これは津山三十人殺しの記録を捜すべきなんじゃないだろうか。もしくは阿部定事件を知りながら解釈の違いを犯した犯人を考えると日本人であるという可能性をやめ、外国人の犯罪記録を捜すのもいいかも知れない。
なんてなことを考えながらまあ読み進めていく次第です。個人的には一男が死んだのだからもういつでも中庭のリュウ壊した方がいんじゃないかなんて事は思う。TSのメンテ終わったしこの辺でお開きにしよう。
PR